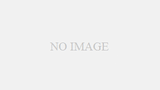SNSやブログに文章を載せてうまく伝わらなかった事がある。というかそんな事ばかりである。
これは最近知ったのだが、文章のスキルやデザインセンスの問題よりも深い問題がある。
それは何かと言うと、文章を書く上での知識よりも深い層にある、感情と欲求の関係である。
同じような発信でも誰が言うかで反応は驚くほど変わる。同じ人が同じような発信をタイミングを変えてしたとしても反応は変わる時がある。
これは平たく言うと波動、とか周波数とかヴァイブスとか言う人の感じであるのだが、それを説明してみる。
まず人間の根源的な部分に何があるかというと、それは欲求である。特に生存に関わる欲求である。
欲求には色々あるのだが、共通して言えるのは満たされていると快、不足していると不快を感じるという事である。
そして欲求と紐付いて感情が生まれる。逆に感情があるから欲求が生まれることもあるが、基本的には深い層にあるのは順に欲求⇨感情⇨知識(認知)である。
で、要は快不快とか感情とかは伝染するのである。オフィスで不機嫌な上司がいるとか、満員電車のストレスとか、果ては社会全体を覆う暗い空気など、狭い範囲も広い範囲も伝染する。
そして文章も、書く時の心の欲求の充足感、どんな感情で書いたかで、伝わり方が変わるというのだ。
さすがに同じ文章で伝わり方が変わるとまでは思えない。(ありそうな気もするけど)これは心が充足している時は、相手のニーズを満たすような親切丁寧な文章が書け、不足感のある時は、自分の不快な欲求を手っ取り早く満たそうと承認欲求を欲したり自慢をしたり乱暴な文章になり、その結果、文体が変わると言うのだ。
これが文章の伝わり方の仕組みである。つまり、日々よい心待ちで明るい気分で物事に当たれると良い結果に繋がりやすいだろう。
何事も継続するなら調子(トーン)のコントロールが大事である。無理はいけない。人それぞれ体力も違うし心の充足感も違うのである。
この事からも物事をうまく達成していくには、協力し合って皆で補い合う社会の仕組みが必要なのである。
調子を維持する事は難しい。これから冬が来るし大変だけど、助け合いの精神で乗り越えましょう。